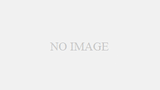コロナ禍を通じて、教育現場にもようやくオンラインツールが本格導入され始めました。
しかし、休校対策でやむを得ず使用しているシーンもあり‥‥。
急速に普及したことによって、セキュリティ意識や、真の利便性についてはあまり議論されないままになっているようにも思います。
こうした事情をふまえた上で、「習い事におけるネット(オンライン)」はどのようにかかわっていくべきなのでしょうか。
オンラインとオフラインは地続きである
2019年、ひとつの大きな潮流となったのが「アフターデジタル」という考え方です。
オンライン、オフラインを分ける考え方はすでに過去のものになっていて、さらにいえばオフラインを土台とする思考も旧来のもの。
つまり、現代はすでにデジタルの中に、オフラインが内包されている状態になっているとする考え方です。
お店で物を買ったり、電車で通学・通勤するといった行動も、監視カメラや電子マネーによってデジタルにデータが記録され、(その気になれば)個人の行動をすべてIDに紐づけることができる。社会は今、そんな「アフターデジタル」の状態になっています。
教室の対面レッスンを例にとっても、
・振替の相談にメールやLINEを使う
・教材をネットで注文する
・月謝を振込する
など、行動がデジタルと接しているシーンはたくさんあります。
メールやLINEは送受信履歴がデータとして残りますし、注文(振込)履歴も同様。自宅練習の参考にと演奏動画をYouTubeで見れば、視聴履歴がバッチリ記録されます。マイナンバーのようなIDにこうした行動を一括で紐づけるテクノロジーがあれば、「対面レッスン」というオフラインの行動も、さまざまなオンラインデータを点として星座のように浮かび上がってくるでしょう。
こうした考えが2020年以降のデジタル社会にもある程度通用するならば、ネットリテラシーも、日常生活のマナーや常識と分けて考えずに地続きのものととらえることができます。
ZOOMやTeamsの危険性はレッスンに「通う」のと同等
普段ネットをあまり使わないという人は、ZOOMやTeamsといったオンラインツールについてセキュリティの不安を感じるかもしれません。
実際、2020年頃には、ZOOMがセキュリティの脆弱性をつかれ、無関係のユーザーがルームに乱入してしまうというハッキング事件が起こっています。一時は米国政府が国内の学校に対してZOOM使用禁止を通達する事態となりました。
しかし、現在ではこの問題は改善され、国内外で多くの団体がZOOMを活用しています。私は、コロナ禍にオンラインレッスンのツールを検討していた時期にこの報道を見たため、当時はWherebyを選択するに至りましたが、現在では別の仕事でZoomやTeamsをバンバン使用しています。
オンラインツールは、脆弱性のカバーが迅速なのも特徴ひとつ。ユーザー側も柔軟な対応をすることが求められると思います。
さらに多くの人が見落としがちなのが、「対面レッスンにも通学にさえ、リスクは常に潜んでいる」という点です。オンラインレッスンと、対面式の教室に通うレッスン。
比較した場合に、オンラインの方が危険が非常に大きいかと問われると、答えはNOでしょう。
例えば、
・通っている道中で怪我をする可能性
・行き合う受講者同士でトラブルになる可能性
は決してゼロではありません。だからこそ、保護者の方はお子さんのレッスンに付き添い、送迎をします。また、身体的な怪我はなくても、そうした現場に遭遇して怖い思いをするリスクもあるでしょう。私にも、習い事に通う途中で事故を目撃したり、路上で一人延々と暴言を吐いている人(酔っ払っている、という時間でもなかった‥‥)を目の当たりにしたことがあり、恐怖を覚えたことがあります。
デジタル環境が急速に発達した今、オンラインにおけるセキュリティの問題は、路上で危険に遭遇するリスクと同程度といえるでしょう。
自宅から一歩出たら100%安全な場所はない。それは安全な日本においてしばしば忘れ去られがちな現実です。
しかし、オンラインが当たり前に存在する現代においては、オンラインで危険に遭遇するリスクも、実生活(オフライン)で遭遇するリスクとさほどパーセンテージに変わりはありません。日常生活と同程度の危機意識をもっていれば、安全なデジタルライフが送れるといえるのではないでしょうか。
とはいえ、「ネットは新しいものだからその場のルールが分からないと不安」と考える方もいると思います。その場合も、人と接する上でのマナーや常識をわきまえていれば大きな問題はありません。
ネットリテラシーは対人マナーと似ている
ネットリテラシーを難しいものと考えたり、デジタルにおける情報漏れを過剰に心配したりする人のなかには、この地続きという概念を知ると少し安心できるかもしれません。
例えば、対面レッスンにおいては、
・レッスンの始まりと終わりに挨拶する
・講師の話を聞く
・運営者の定めたルールや規約を守る
のような基本的な点を守ることが求められます。
これは子どもの生徒さんだけでなく、成人の生徒さんにもいえること。自分より年下の講師に教わる場合でも挨拶をせずにレッスン中ずっと踏ん反り返っている方はいないと思います。
そして、立ち入り禁止と書いてあるスタッフルームにずかずか入り込む、スタジオに入るためのパスワードを第三者に触れ回る、講師やスタッフを盗撮するといった行為をする人もいないでしょう。なかにはいるかもしれませんが、犯罪スレスレ(もはやアウト?)のため、訴えられずとも出入り禁止になる可能性は高いと思われます。
また、ルールを無視したことで怪我をしたり不利益を被ることもあり得ます。
これは、そのままネットやデジタルツールを使う時に必要なこと、気をつけることに当てはまります。
つまり、運営者の定めたルールを守って使うこと。ここでいう運営者とは、WherebyやZOOM、Skypeといったサービスの運営会社と、教室を運営する者の両者をさします。
なお、ルールや規約として定められていないことは、積極的に聞いてみることをオススメします。教室や講師は、あくまで「提供する」目線に立ってオンラインレッスンを実施しています。そのため、生徒さん側のジレンマに気づきにくいことも。受講者が不便に感じるポイントを確認することで、よりよい内容を提供できるようになるでしょう。
聞いてから実行がベターなオンラインの行動
オンラインレッスンは、急遽始めたという教室や先生も多くルール作り自体いきとどかないという運営者も多いかと思います。
そこで受講者がレッスンを受ける時、こんなアクションは講師に聞いてからの方が波風が立たないかな、と思ったことをまとめました。教室や講師によってルールや感じ方には違いがあると思うので、参考程度に見ていただけたら嬉しいです。
録画・スクショ
路上やロビーでのライブパフォーマンスの場合も、写真OK、録画NGのケースは結構あります。自宅練習や振り返りが目的でも、録画不可というルールを定めている先生もいらっしゃるので、レッスン最初に聞いておくと安心かと思います。
また、スクリーンショットは、楽譜や書籍の場合、著作権侵害につながるリスクを考慮して禁止している教室もあります。
録音
個人的にはそこまで気にならないですが、演奏家としての活動が主な先生や、講演会をメインに活躍されているインストラクターの方は、レッスン内容の録音がNGという場合も。
録画よりもハードルは低いですが、念のため「レッスンを録音してもいいですか?」と一言断っておく方がいいかもしれません。
レッスン後のフォロー先
オンラインレッスン終了後に質問やフォローを受け付けている先生は多いと思います。
私も、音源を送るためにLINEを使ったり、Skypeのチャット画面でレッスン後に次回までの課題を送ったりしています。
個人の先生なら自分用のアカウントを使っているので問題ないかと思いますが、大手教室の場合、「火曜日しかチャットを確認できない」、「レッスン時間外は専用のサポート対応デスクにメッセージが届く仕様になっている」といったケースもあるので、レッスン後のフォローに応じてくれるかどうか、また課題送付先は同じアカウントでよいのかなど、不安に思った場合は聞いておくとよいでしょう。
まとめ:オンラインもオフラインも向こうにいるのは「人」
オンラインレッスンも、対面レッスンも、相対するのは「人」であり、生身の人間とやりとりしていることを忘れてはならないと考えています。
音楽教室の場合、教室ごとに環境や規約が異なっているのと同様に、オンラインレッスンもそれぞれのルールや考え方によって運営されています。新しい技術だからといって必要以上にリスクをおそれることなく、講師も受講者の皆さまもよりよい形を一緒に模索していけると良いですよね。